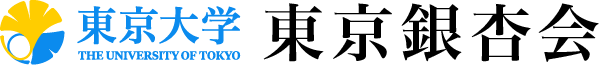第32回江戸・東京を知る会 神楽坂散策が2025年10月4日(土)に10名の参加を得て開催されました。地元でまちづくりを指導する山下馨さん(1977工)による丁寧な案内を頂きながら飯田橋駅の西口にある牛込見附を皮切りに善國時、赤城神社などを訪問しました。
最初の訪問地は、飯田橋駅西口すぐにある牛込見附跡です。外堀を見下ろす大きな石垣が残っています。三代将軍徳川家光は、火事で焼けた江戸城からこの牛込見附を通り神楽坂を登って老中酒井忠勝の屋敷に移って幕政を執ったという話が残っています。山下さんのお話では、この屋敷を防備のため竹や丸太で荒く組んで臨時の囲い、つまり矢来で囲ったことが牛込矢来町の起こりとのことでした。
次に訪問したのは、神楽坂の上にある善國寺です。江戸時代中期の寛政4年(1792)に移転してきた日蓮宗池上本門寺の末寺で、神楽坂の中心として親しまれ続けています。お祀りしている毘沙門天は別名多聞天と称し、仏界の天部に於ける四天王の一人で北方の守護神、開運厄除けの神として、江戸時代から後々まで多くの参拝者を集めて賑わいを見せています。
神社ではありませんが境内に一対の狛犬ならぬ狛寅の石像があり、これも江戸時代の作で新宿区の指定有形民俗文化財です。なお境内には浄行菩薩、出世稲荷神社もあり、門柱にはロッキード事件で有名な児玉誉士夫の名が標されているそうです。また、TVドラマ「拝啓、父上様」で人気グループ嵐の二宮和也が主演して以来、嵐ファンの聖地として知られる様になり多くの絵馬が奉納されています。
神楽坂も飯田橋駅からケヤキ並木のある坂をのぼって並木が尽きると大久保通との交差点に出ます。交差点を渡って先に進むと、商店街も地元目線になり、子供連れの家族が多く歩き、裏手は住宅街で日常的な街になってきます。そこから右に入ると大樹の森の中地元の鎮守である赤城神社が見えてきます。江戸時代は徳川幕府により江戸大社の一つとされ、牛込の鎮守として信仰を集めました。御祭神は「磐筒雄命(いわつつおのみこと)」「赤城姫命(あかぎひめのみこと)」で、平成22年(2010)に完成した新社殿は建築家・隈研吾(1977工)によるものです。
神楽坂には、空襲で焼けた後に再建した建物の中で、戦前からの文化活動拠点や、戦後の新しい時代に夢を託した建物など、相当数の地域の宝ともなっている建物が存在しています。その中の7棟は、国の文化財台帳に登録されています。神楽坂の街では、地元の方のご努力でその価値を維持しています。その事例として、商店街から少し奥に入ると、道路付けもわるくなりなかなか建て替えが進まないエリアでの古い住宅を対象にした取り組みを見学させていただきました。
最後に、神楽坂といえば花街のイメージが濃厚ですが、ケヤキ並木の裏通りの狭くてアップダウンのある路地伝いに広がる、小ぢんまりとしながらも風情をたたえた料理屋などを外から眺めながら通り過ぎて本日の街歩きを終了しました。
交流会は、山下さんお勧めの中華料理店縁香園で開催しました。ちょうどこの日の午後は自民党の総裁選が終わった直後で、初の女性総裁選出ということは初の女性首相誕生かという話題もあり、さらには参加の皆様それぞれの街歩きの感想も交えながら盛り上がりのあるひと時を過ごすことができました。
なお、詳しい開催報告は10月末発行の銀杏会ニュース170号をご覧ください。
(文責:世話人 小川富由1977工、写真:小川富由 渡口潔1975工)