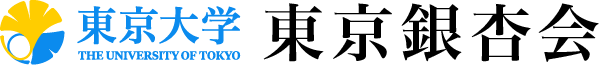2025年3月1日(土)、会員等12名が東京メトロ有楽町線豊洲駅に集合し、「鉄道遺構めぐり」を行いました。
まず、豊洲駅から徒歩で「晴海橋梁(東京都港湾局専用線)」へと移動しました。この晴海橋梁は、国鉄越中島支線の越中島駅(現越中島貨物駅)から豊洲石炭埠頭までを結ぶ、東京都港湾局専用線(深川線)における「晴海運河に架かる橋梁」として、1957年に供用開始しました。その後、1989年に当該貨物列車が最終運行となり、それと同時にこの晴海橋梁も供用廃止となりましたが、その歴史的価値を鑑み、未来へ遺すために公園内の遊歩道として改修する工事を行っているところでした。また、現地には、その歴史を示す案内板が設置されていましたが、そこで使われている和暦表記に対して「西暦で書いてくれないと、読んだ人が現在と比較する際に分かりにくいですね」等、長年国民の皆様のために奉仕してきた本会の参加者らしい意見がありました。
次に、豊洲駅から「ゆりかもめ(東京臨海新交通臨海線)」に乗り、汐留駅へと移動しました。当初の予定ではバスで移動することになっていましたが、当会主宰の岩村敬副会長から小学生の参加者への配慮があり、「ゆりかもめ」で移動することに変更となりました。「ゆりかもめ」の先頭車は、大きな窓のある最前列からの眺めがとても良く、東京の臨海部が一望に見渡せるため、小学生でも楽しむことができ、かつ飽きずに目的地へと到達することができました。汐留駅に着くと、そこから徒歩で「旧新橋停車場機関車用転車台」へと移動しました。この遺構は、転車台の基礎石が円形に配置されたもので、現地の地面にはその説明プレートが埋め込まれていました。また、「汐留イタリア街」というイタリア風建築を模した再開発エリアの中心広場内に存在し、過去と現在とを行き来するような感覚の遺構となっていました。
その次は、「汐留イタリア街」から徒歩で東側へと移動し、「浜離宮前踏切跡」という遺構を見学しました。この遺構は、都会の交差点の一角にトラ模様の踏切信号機が堂々と立っているもので、小学生が遠くから見ても、「あ!踏切があったよ!!」と分かるような遺構でした。また、この踏切信号機が面する道路は朝日新聞本社脇へと続いており、約150年前の鉄道開業時に誕生した初代新橋駅(後の汐留貨物駅)から築地市場に延びていた緩いカーブを描く「引き込み線」を、その後道路にしたものでした。加えて、現地にて、岩村副会長から「昔は今ほどトラックや道路が発達していなかったので、この線を使って全国から築地市場へ(各種品目を)鉄道で運び入れていたわけですよ」等の解説がありました。
またその次は、日本テレビ社屋の近くまで徒歩で移動し、「旧新橋停車場(復元駅舎、鉄道歴史展示室等)」の見学を行いました。こちらは、電通本社やロイヤルパークホテルといった超高層ビルが建ち並ぶ汐留の再開発エリア内にあるもので、当時の面影を再現したとても良い建物及びホームとなっていました。また、単に再現するだけでなく、鉄道遺構自体も存在かつ展示されており、過去の歴史を未来へとつなげる重要な役目も負っていました。建物内には、鉄道の歴史の展示だけではなく、「鉄道少年の部屋」の再現やお茶の「伊藤園のアンテナショップ」等があり、鉄道ファンではない人たちも楽しめるよう工夫された施設になっていました。本会当日も、カップルや家族連れのお客様が多く訪れていました。
そして、昼食の時間帯となりましたので、香川県と愛媛県のアンテナショップに併設されたレストラン「せとうち旬彩館 かおりひめ」へと移動し、懇親会を行いました。香川県、愛媛県の郷土食豊かなメニューで、愛媛のみかんジュースを飲むことができ、「〆(しめ)」には讃岐うどんが提供されるという、大変分かり易くかつ美味しいお店でした。
最後に、JR新橋駅へと移動し、鉄道ファンならずとも知っている有名な鉄道唱歌の記念碑を蒸気機関車D51の動輪とともに見学した後、駅前広場にある蒸気機関車「C11 292」の威風堂々たる車体を眺めて、解散となりました。なお、解散の際には、1日3回鳴る汽笛(本寄稿時点において正午・15時・18時)を聞くことができ、家路につく当参加者を蒸気機関車が見送っているようでした。
(文責:岡田幸村 2017 公共院、写真:渡口 潔 1975 工)