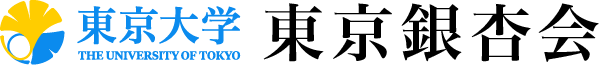2024年度第3回銀杏懇話会は、樋口真人弁護士・元警察庁(1982法)を講師にお迎えして「犯罪グループの最近の動向 ~匿名・流動型犯罪グループを中心に~」をテーマに3月6日(木曜日)、四谷の主婦会館プラザエフ地下2階クラルテで開催しました。
樋口さんは、1982年東京大学法学部卒業後、警察庁に入庁し、徳島県警察・大阪府警察・警視庁・警察庁の捜査第二課長、熊本県警察・福岡県警察の本部長、東京都青少年・治安対策本部長等を経て、2016年8月大阪府警察本部長を最後に退職。同年10月弁護士登録をされています。
警察在職中は「地面師詐欺事件」・「取込詐欺事件」・「M資金詐欺」等の捜査や全国で唯一「特定危険指定暴力団に」指定されている「工藤會」の「壊滅作戦」の指揮等に従事し実績を挙げられました。
ご講演の概要は以下の通りです。

はじめに
現場警察の経験が多く、捜査二課長や警察本部長在任中に多くの事件捜査に従事し「事件持ち」などと言われた。そのような経験から、犯罪グループとの闘いには社会全体で取り組む総合的な対策が必要だと強調したい。
1.暴力団とは
暴力団は「人に恐怖を与え私的な目的を達成しようとする反社会的集団」であり、その本質は「金になることなら何でもする」ということである。
2.「暴力団対策法」の意義
暴対法は改正が重ねられ、組長責任、特定抗争指定、事務所使用制限命令などが追加され、工藤會対策などで有効に機能した。しかし、暴対法も被害者からの協力がなければその多くの規定も無力である。
3.「暴力団排除条例」の意義
暴排条例は市民の暴排意識の徹底と市民の協力確保に貢献したが、福岡北九州では「暴力団お断り」の看板を掲げた店舗が工藤會により襲撃されるなどの事件も発生した。
4.「準暴力団」(半グレ)
「準暴力団」(「半グレ」)と呼ばれる集団は暴力団の「下部組織・協力組織」であり、元暴力団員や現役暴力団員がメンバーになっているケースも多く、実質的に暴力団勢力そのものである。
5.「匿名・流動型犯罪グループ(「トクリュウ」)
「暴力団」という言葉は昭和40年代から社会にも定着したが、「匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)」と言われる犯罪グループには「売春暴力団」と言ってもよいグループなども存在し、また、暴力団の「下部組織・協力組織」であり、トクリュウも暴力団勢力そのものである。「暴力団が減ったのでトクリュウなどの新たな犯罪グループが台頭してきた」などと言われることがあるが、トクリュウは増大しており、暴力団勢力はそれほど減っていない。
6.犯罪グループの最近の動向
犯罪グループは社会情勢に応じて資金源を多様化させ、手口もより悪質・巧妙化させている。犯罪の国際化が進み、犯罪グループの多国籍化も進み犯罪拠点を国外に置く例も増えている。AIやディープフェイク技術を使った「なりすまし詐欺」など、テクノロジーを悪用した新たな犯罪手法も出現している。犯罪グループが警察官までも取り込む事例もみられる。
7.「犯罪グループ」と闘う上には「総合的な対策」が必要
犯罪グループ対策には総合的なアプローチが必要で、犯罪グループに付け込まれない制度設計、捜査機関による検挙、行政処分、教育啓発などが重要である。
講演終了後は、質疑応答があり、懇親会が開催されました。懇親会は、嶋津昭会長(1967法)のご挨拶と乾杯のご発声で始まり、樋口講師を囲んで、質疑応答や、参加者同士の意見交換の輪が広がりました。中締めは氏家純一会長代理(1969経)のご挨拶で、名残惜しくも会は終了しました。さらに、講師を交えた有志は四谷の某所での二次会で盛り上がりました。
講演の詳細報告は、今秋発刊の会報『銀杏』第26号に掲載予定です。ぜひそちらもご覧いただきたいと存じます。
(文責:小川富由 1977工)
講演会の模様



懇親会の様子