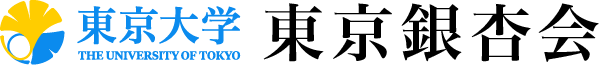2050年度第1回銀杏懇話会は、1986年工学部ご卒業の桑野玲子東京大学生産技術研究所教授を講師にお迎えして「都市に潜む落とし穴―地下埋設インフラの逆襲」をテーマに7月15日(火曜日)、四谷の主婦会館プラザエフ地下2階クラルテで開催されました。
桑野さんは、1986年東京大学工学部土木工学科卒業。1988年同修士課程修了。1989年大成建設土木本部土木設計部。1999年ロンドンインペリアルカレッジにて学位取得、東京大学大学院工学系研究科社会基盤工学科助手、講師。2002年土木研究所主任研究員、2006年東京大学生産技術研究所助教授・准教授を経て2013年より現職を勤められておられます。
都市の成熟に伴い道路下に埋設されたインフラの老朽化が進み、路面下に道路陥没を引き起こす事例が増えており、今年1月には埼玉県八潮市の流域下水管の破損により大規模陥没が起こり、走行中のトラックを巻き込む人身事故が起きました。ご講演は、揺るがないはずの地面が突然崩落するような陥没現象がどのような過程で起こるのか、都市の地下に潜む空洞の実態と陥没に至るメカニズム、さらにその対策について、以下の観点から行われました。

最近の地盤陥没事例
八潮市のほか、ニュースになったものとしては地下鉄工事に起因した博多駅前、高速道路工事に起因した調布市の住宅地などで起こっている。
都市の道路陥没の実態
道路の陥没は、新聞沙汰のケースはたまにしか起きないが、実は国道、県道、市町村道で毎年約1万件と結構頻発している。結局のところ、道路の下に下水とか上水とかが埋まっている所はそれの老朽化によって道路陥没が起きてしまう、そういう宿命を持っている。
下水管の老朽化に起因する道路陥没
八潮のように下水の管路に起因する道路陥没の件数というのは、例えば、令和4年度の場合、2,600件となっている。
路面下空洞の調査方法と発生状況
空洞には地表から2m以内の浅層空洞と深層空洞に大別され、浅層空洞は地中レーダ探査などで知見蓄積があるが、八潮のような深層空洞はその手法が使えず実態が不明である。
空洞生成・拡大の要因
下水管の施工不良、老朽化、他の埋設管工事の影響、地震など多様な要因が挙げられるが、不明とされるものもある。
空洞の拡大メカニズム
水と土が下水管から出ていって、小さくて狭めの穴できるのが最初だが、この状態だと土の上の所にアーチングという土が自分自身で自分を支えるような効果があるので陥没はしない。だが、だんだん広がってくると、上を支えるアーチングが働く余地がなくなって最終的には陥没する。もし浅い所で土砂の継続的な流出が起きたら、最終的に起きる陥没というのも小さい。深い所に流出のもとがあったら、知らないうちに結構大きく広がって大きな陥没になる。これが八潮のケースである。地中埋設インフラが老朽化して破損し、その拡大を助長してしまう雨や地震があって土砂の流出の経路というのが確保されると、空洞の生成や拡大が一気に広がる
空洞の陥没危険度評価
空洞ができやすい環境要件には、地中埋設物が複層している、流出しやすい土がある、地質、地形で地下水が集まりやすいような所、掘削工事の履歴があるなどの要件が挙げられる。定量的には、実験や国土交通省の国道の空洞や陥没の事例から分析すると、陥没の危険度は、空洞の深さの5倍以上にはならないという部分が大体合致している。
老朽下水管起因空洞の事例
地下水よりも下に埋設された下水に侵入水や不明水が入ってくるっていうのはそんなに珍しいことではないらしい。下水管理者は、漏水はしていても、損傷しているという認識を持っていない。だが、実験でわずか2ミリほどの開口部でも、土砂が引き込まれて空洞ができるということが分かった。下水の管理者には、不明水が入ってくる、侵入水がある、水が入るということは、状況次第では土も入る、空洞もできるということを認識していただく必要がある。
空洞拡大における地震の影響
地震があるとその影響で陥没が増える。熊本地震の前後で、いわゆる陥没危険度が高い空洞の比率がどう変化したかというのを調べた結果、普段は平常時非常に危険度の高いケースが大体18%ぐらいだったのが、熊本地震の後には空洞の数も増え、その比率が60%に増えているということが分かっている。
八潮陥没と得られた教訓
八潮のような大陥没は一定の条件が重なるとまた起こるかもしれない。その一定の条件に当てはまるような所を事前に抽出して、対策を取っていくことが必要である。埋設のインフラというのは、私たちの生活を陰で支えてくれるライフラインで、なくてはならないものだが、普段、下に埋まって忘れられている。適切に維持、管理をしていかないと、逆襲されるというか、負の遺産になりかねない。今回の事故はその教訓を与えてくれている。
講演終了後は、質疑応答があり、懇親会が開催されました。懇親会は、嶋津昭会長(1967法)のご挨拶と氏家純一会長代理(1969経)の乾杯のご発声で始まり、桑野講師を囲んで質疑応答や、参加者同士の意見交換の輪が広がりました。土木学科の同期生も多数お集まりになって懇親に花を添えていただきました。中締めは杉本文雄代表幹事(1977工)ご挨拶で、名残惜しくも会は終了しました。
講演の詳細報告は、今秋発刊の会報銀杏第26号に掲載予定です。ぜひそちらもご覧いただきたいと存じます。
(文責:小川富由 1977工、写真:渡口 潔 1975工 小川富由 1977工)

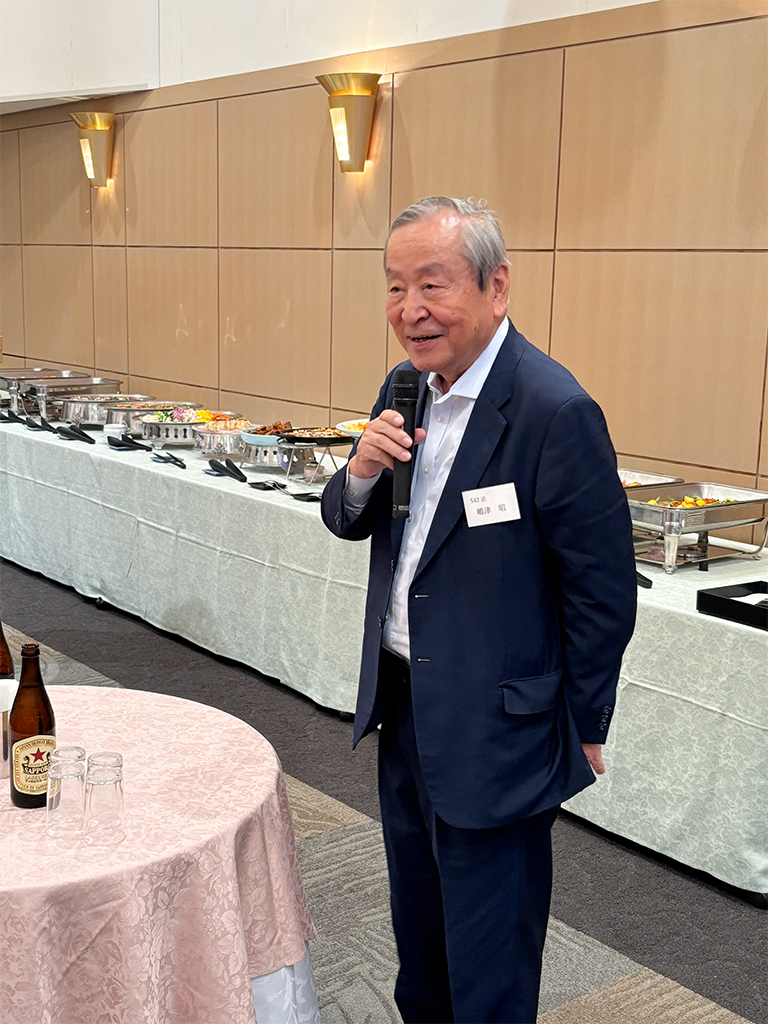

懇親会の様子